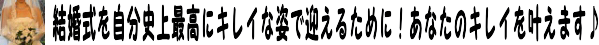結婚式の費用!新郎新婦の負担割合は?
※当サイトではアフィリエイト・アドセンス広告を利用しています。
すべて、通常価格1,250円(税込)のところkindle版(電子書籍)が
今だけの期間限定で20%OFFとなる1,000円(税込)で販売中です!
このチャンスを見逃さないでくださいね♪
さらに月額制サービスなら、すべて【無料】で読むことができるんです!

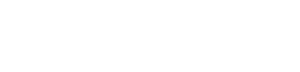
いざ、結婚式を挙行しようと思い立った時に
現実的な最初の問題になるのは、やはり費用面ではないでしょうか?
結婚式を挙げた先輩カップルは、どのようにして
新郎新婦で結婚式の費用を負担したのか、気になるところですよね。
ここでは、先輩カップルの実例を紹介しながら、結婚式の費用について
新郎新婦の負担割合を考えていきます。
自分たちに合った、費用の内訳や予算の相場を確認しつつ
ぜひ思い出に残る結婚式を、実現させてみましょう!
目次
後でモメない結婚式の費用分担~5ヶ条~

初めに、トラブルに至りやすい結婚式の費用にまつわる
分担の詳細について、紐解いていきます。
1.両家の家族に相談する
結婚は、新郎新婦2人だけのものでなく、新郎と新婦の家が
2人の結婚によって家族になるものですよね、
だからこそ、費用についても、両家の家族には
事前に相談しておくのが、後々モメないためにも
非常に大事なポイントであると言えます。
もちろん、費用負担の割合について、両家に話すのは
顔合わせが済み、お互いの人となりが分かった後にしましょう。
自分達が折半する意思を持っていても、両家の地域性・風習などが
関わってくる場合もあるので、事前に確認しておきたいところ!
「2人の結婚式だからと、費用分担を決めていたら、後々
新郎側の両親に、恥をかかせないでと泣かれた」
「共働きだったので、折半しようと計画していたら
新郎の両親に費用を出させてほしいと言われた」
などといった、先輩花嫁さんの声も沢たくさんあるので
ぜひあなたも、それぞれの声を参考にしてみてくださいね。
2.式場スタッフに相談する
式場のスタッフは結婚式のスペシャリストです。
だからこそ、費用面を含めて、分からないことはぜひ
式場にいるスタッフさんに、適宜確認しておきましょう。
また、両親へ話す上で、費用などの金銭的な話題を話しづらい
という場合は、式場スタッフを交えて話し合うのも
1つの方法であると言えます。
3.2人で限度額を決めておく
結婚式を挙行する上で、そもそもの限度額を決めておくことは
根本的な必須項目であると言っても、過言ではありません。
例えば、ご祝儀で賄いきれない分は、新郎が負担してみたり
花嫁のエステや美容代は花嫁負担になるので、実数的には6:4で
新郎側が多めに折半するなど。
折半の方法や限度額をあらかじめ決めておくことで
よりスムーズに、結婚式を成功させられると言える他
先輩花嫁さんからは、以下の声が挙げられました。
「予算を越える場合、お互いがどこまで払うか先に決めておいた」
「挙式以上にその後の生活が大事なので
限度額を決め、その範囲内で収まるような内容選びを徹底した」
4.結婚前から共通の口座を持つ
お2人が結婚後の生活費などで使う口座を新しく作っておくことも
重要な金銭管理のコツであると言えます!
そこには、結婚式で「使える金額」を入れておき、足りない場合は
どのように賄うべきか、余れば今後の生活資金に、と考えられます。
2人の「共通口座」であれば、折半というシビアな捉え方になりにくく
「共同費用」という感覚を育みやすくなります。
両家から、それぞれに費用を出してもらう場合も
共通口座に入れて、2人で一緒に使うという先輩カップルも
比較的多くいらっしゃるので、ぜひ参考にしてみましょう。
5.ゲストの人数割りを使う
新郎と新婦で、招待するゲストの数が大きく違う場合に
有効性を発揮しやすいのが、ゲストの人数割りであると言えます。
通常は、新郎新婦でテーブルを半分ずつ使用してゲストを呼びますが
片方のゲストが多い場合は、人数割りを提案しておくと
後でモヤモヤした気持ちに陥りにくいのが、最大の特徴です。
「全額折半にしたが、新郎側の方が招待客が多かったので
新郎側にもう少し負担してほしかった」
「新郎側の親戚が多く参加したので、テーブルに関わる装飾は折半し
引き出物は人数割りしました」
といった、先輩花嫁さんの声も挙げられたので
ぜひこちらも、参考にしてみてはいかがでしょうか?
負担割合は遅くても3ヵ月前までに決める

両家に相談した上で、ご両親から援助してもらえる場合は
半年程前の時点で、負担割合を決めておくのが一般的であると言えます。
お2人でやり繰りする場合は、ある程度、費用を明確化させてからの方が
負担割合を出しやすいので、先輩カップルの多くは
遅くとも、3ヵ月前までに決める、という声が多く挙げられます。
3ヵ月前にもなると、金額の詳細が1,000円単位で確定し始めるので
どこを削るか、どこをグレードアップするかなど
より細かい内容に目を配りながら、それぞれの金額を算出できます。
最初の見積もりでは、あらゆる部分にこだわっていても
現実は金額との相談になるケースがほとんどでもある結婚式。
この時、花嫁さんのこだわりが強い場合には、新婦側が若干多めに
負担する、というカップルも、少なくありませんが、以下の要領で
結婚式を乗り切った先輩花嫁さんの声も、同時に挙げておきましょう!
「生花のボリュームには、妥協せずにこだわりたかったので
装飾花のグレードは上げましたが、装飾花代は新婦側で捻出しました」
「新郎側で、楽器の持ち込み・演奏の余興を企画したので
楽器のレンタル料が発生しましたが、レンタル料や控室代は
新郎側で負担してもらいました」
結婚式に向けた費用について話し合おう!
ここまでご紹介してきた、結婚式の費用に関する内容について
少しでも、今後の参考にしていただけましたか?
筆者の場合、両家の顔合わせの段階で、ご祝儀をはみ出す部分は
両家の両親が負担する、という方針を立てられたので、結婚前の約1年間は
お互いに実家暮らしで、家賃分を貯金、2人の共通口座で貯金しました。
どの結婚式においても、新郎新婦の考え方が大前提であるものの
両親は両親で、結婚式の費用に関する考えを持っているケースは
意外にも、決して少なくありません。
だからこそ、この部分は、なるべく早めの段階で確認しておきたいところ―
その上で、先輩カップルたちの成功の秘訣をまとめると
以下の3点が挙げれれることが分かりましたよね。
- 両家の両親には早めに相談しておく
- 予算オーバーに際する折半方法を決めておく
- 式場スタッフに相談する
両家が費用を出してくれる場合には、式場にお願いすることで
各家庭用の見積もりを作成してくれるので、費用の内訳が
完全なる折半でない場合も、気兼ねなく見積もりを渡せます。
これから結婚式の費用を、どの割合で負担しようか考えているのであれば
まずは、両親の意見も聞いた上で、改めて新郎新婦で決めてみましょう!
.
すべて、通常価格1,250円(税込)のところkindle版(電子書籍)が
今だけの期間限定で20%OFFとなる1,000円(税込)で販売中です!
このチャンスを見逃さないでくださいね♪
さらに月額制サービスなら、すべて【無料】で読むことができるんです!

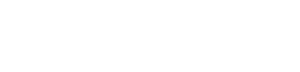
この記事を読まれた方は次にこの記事も読まれています